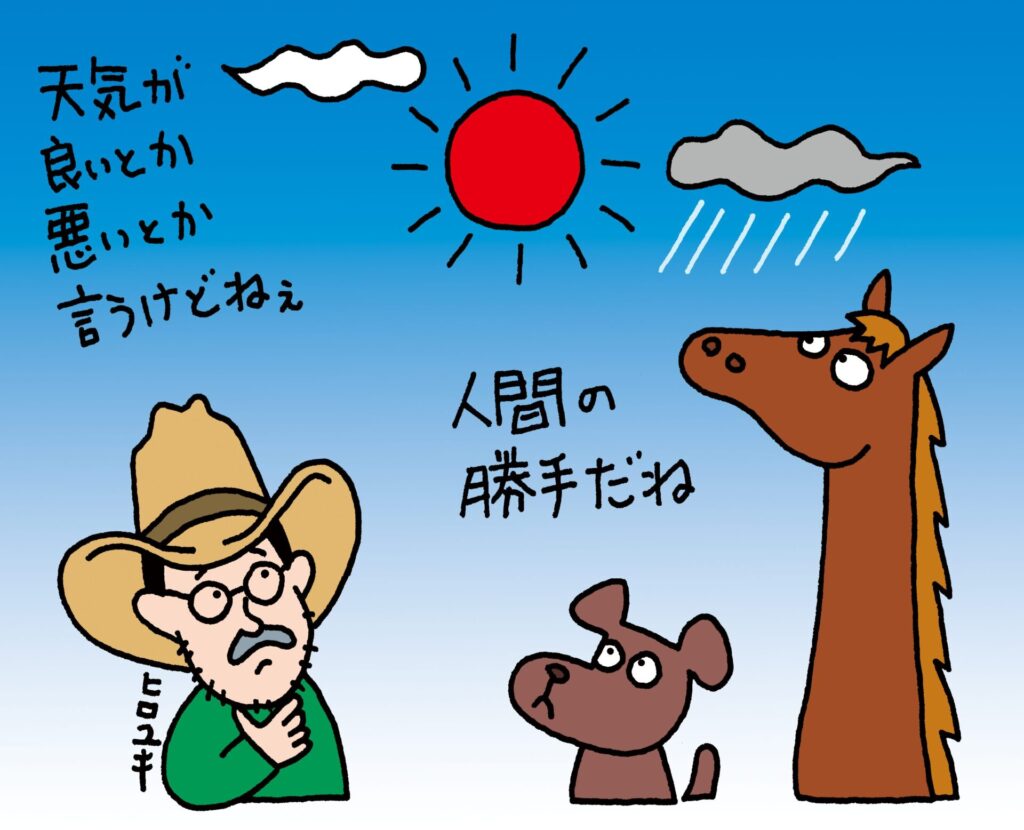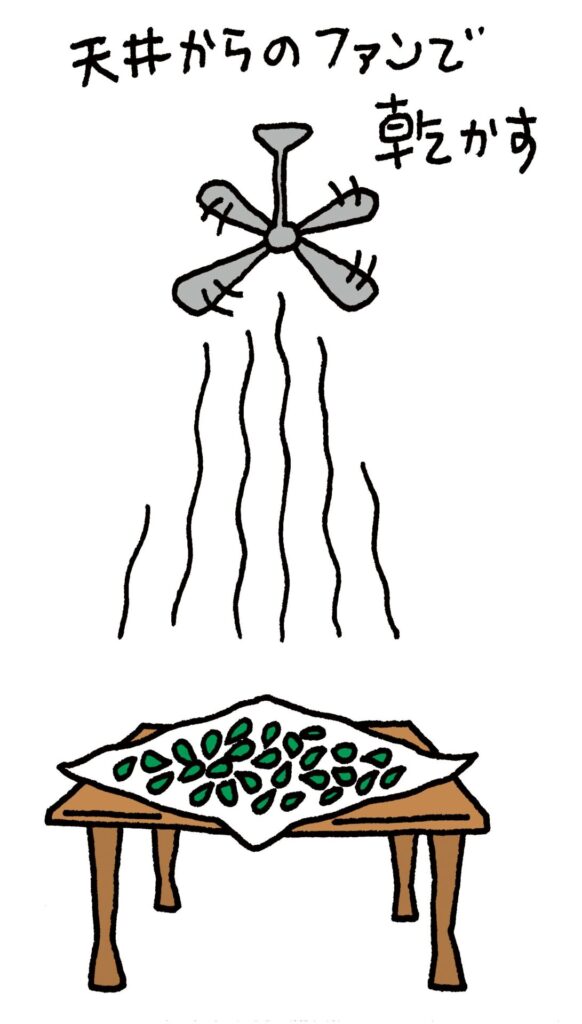気候変動とホップ栽培について
Contents
天気は【天の気分】
晴れていると「良い天気ですね」と挨拶をします。
雨になると「天気が悪くて嫌だなぁ」とボヤきます。
果たしてそうなんでしょうか?
ホップを育てていると、天気はいつも「良く」もあり「悪く」もあると感じます。
天気は【天の気分】次第ですから、それを「良い」とか「悪い」と呼ぶのは、人間の勝手です。
そして、その「勝手」も人間の立場によって、良いと感じたり悪いと感じたりするものです。
なんだか、哲学的(?)な感じに始まりましたが、農業にとっては「晴れ」がいつもいつも「良い天気!」と言えない時があるということを知ったからです。
ホップも時期によって水が必要
ホップは根腐れを起こすことがあるので、水持ちが良い土壌よりも水はけの良い土壌が適していると言われます。
しかし、植物ですから、まったく水が必要ないというわけではありません。
特に、毛花が咲き、毬花が大きくなる時期には水が必要です。
とは言え、今までの年はほとんど【水撒き】をしたことがなく、自然の降水に任せていました。
ところが、今年はまったく雨が降らない時期が1ヶ月続きました。
その上、連日気温が35℃を越し、道路脇の温度計が40℃を示す日もありました。
こんな年は、はじめてです。
前々回、空梅雨の対策として「農業用水からエンジンポンプで水を汲み上げて、ホップ畑に撒く」という話を書きましたが、その「農業用水」がチョロチョロとしか流れていなかったり、完全に枯れてしまう日までありました。
完全に干上がった農業用水路。本来はたっぷりと水があるはず。
川も完全に干上がり、川底の石畳が道路のように見える。
ホップの葉が枯れだし、雑草まで枯れだす始末
このような日が続き、ホップの葉が枯れ始めました。
はじめは、ベト病などの病気を疑ったのですが、写真を撮って京都府の機関【丹後農業改良普及センター】に問い合わせたところ、
・全体的に葉が黄化している。ただし、斑点ではない。
・高温乾燥が続いているため、カビが発生しにくい環境である。
・落ち葉のカビの跡(白っぽいかすれ)が見られない。
というポイントから
・病気ではなく日焼けや水不足による枯死と考えられる。
また、
・7/17あたりで強風が続いたことから、葉が擦れて傷がつき、傷口から水が抜けていったことが葉の枯れに拍車をかけたと考えられる。
・気象条件に起因するため、残念ながら対処法がありません。早くまとまった雨が降ってくれるよう、祈るばかりです。
との回答をいただきました。
祈ってはみたものの雨が降るわけでもなく、毛花のまま枯れたり、毬花が枯れたりし出し、ついには雑草まで枯れ始めました。
行政の対応は? 地域のコミュニティは?
この事態に行政も手をこまねいて見ているわけにもいかず、8/5から【宮津湾浄化センターの放流水を農業用水として活用】できるようになりました。
ただし、「給水用車両」で行くまたは「貯水タンク(ローリータンク)やエンジンポンプやホースを持参」し、事前の申し込みも必要とのことでした。
グーグルマップによると私の圃場から宮津湾浄化センターまでは車で片道33分かかります。
100リッターのローリータンクを2つ載せての走行だともう少しかかるかもしれません。
時間がもったいないです。
また、時間が10時〜16時というのも問題です。
この暑さだと、日中に水を撒くと「お湯を撒いている」ようなことになり根にとって悪影響を及ぼします。
そこで、農業用水路の上流に水を汲みに行くという方法をとりました。
私の圃場の地域は大江山連山の麓で、その水脈からの水はちょっとのことでは枯れません。
この水は上流の田んぼから順番に使われているのですが、その田んぼの方々にお願いして汲ませてもらうのです。
朝と夕方に200リットルずつくらいであれば、「まー、ええで」ということになりました。
【地元の農業コミュニティ】は頼りになります。
軽トラックの荷台に100リットルのローリータンクを2つ載せて、合計200リットルの水を汲ませてもらえれば、私のホップ圃場の1/4ほどの面積に水が撒けます。
朝と夕方に撒けば1日で半分の面積が撒けるので、2日で全体に撒けることになります。
ちなみにこの作業は1回2時間くらいかかるので、朝は午前5時から7時、夕方は午後4時から6時が水撒きタイムです。
1日4時間が水撒きとは……。
一転して雨の日が続く
雨の降らなかった時期は散水でなんとか乗り切りましたが、今度は一転8/5の夜から雨が降り始めました。
その後、山陰から近畿、北陸にかけての日本海側では雨が続き、8/7には金沢で線状降水帯が発生したようにかなりまとまった雨が降りました。ドカ雨です。
8/8、9と一旦やみましたが8/10から12まで雨が降り続けました。
雨は、ホップの成長には必要ですが、収穫には適していません。
与謝野では収穫したホップを真空パックして冷凍しますが、濡れた毬花を冷凍すると無駄な水分が凍ってしまうからです。
そのため、収穫したら【送風で乾燥】させる必要があります。
水撒きのための早起きからは解放されましたが、送風乾燥の時間を考えて朝早くから摘まなければならなくなったのです。
雨は、降らなければ大変ですし、降ればまた大変です。
塩梅よく降っていただければ助かるのですが……。
天気は天の気分次第なので文句は言えません。
ビールは農作物があってこそ
今年は、収穫が始まった時点で毬花のサイズも大きく香りもしっかりあったので【豊作】を期待したのですが、毛花の時期に水が足りず、慌てて散水しましたが時すでに遅しだったのか?毛花が毬花になってくれません。
一転して【凶作】になってしまいそうです。
異常気象が「それが当たり前」となるのかもしれないとすれば、どうすれば良いのでしょうか?
特に、水の確保や効率の良い水撒きの方法などを考える必要が出てきたと思います。
周りの田んぼを見ていても、稲は今年も豊作にはならないような気がします。
米不足がまた訪れるような予感がします。
異常気象、気候変動は世界的な傾向とも言われています。
ヨーロッパやアメリカでも40℃を超える場所があるとのことです。
与謝野だけでなく日本全国、そして世界でもホップが凶作でないことを願うばかりです。
ネット検索すると「地球温暖化の影響でホップ収量の変動が懸念されている」との情報も出てきています。
世界的な規模で考えても、原料の国産化は進めていく必要があると考えられます。
私も、ホップを栽培をすることで【世界的な気候変動】についても意識が高まってきました。
【ビール】はホップや麦という【農作物】があってこそ生まれるお酒だということが一層身に沁みる、異常な暑さと不安定な降水量の夏です。
つづく
この著者の他の記事
- ブロアーによる楽な【株開き】とは(2025.12.1)
- ホップコラム 2025年 最終回
日本産ホップ、この1年、そしてこの10年を振り返る(2025.10.1) - 採れたホップはどこに売れば良いの?(2025.9.15)
- 不作の年でも生ホップビールを楽しむために(2025.9.1)
- ホップ畑の生きもの達(2025.8.1)
- 暑さはサマータイム、空梅雨はエンジンポンプで対応?(2025.7.15)
- ホップの価格、保存、使いわけについて考える(2025.7.1)
- ホップ栽培、バジェットとリターンのお話(2025.6.15)
- ホップの肥料について考える(2025.6.1)
- 藤原ヒロユキのホップ栽培日記 in 与謝野町 道具編
その⑦「収穫に必要な道具」(2024.8.5)